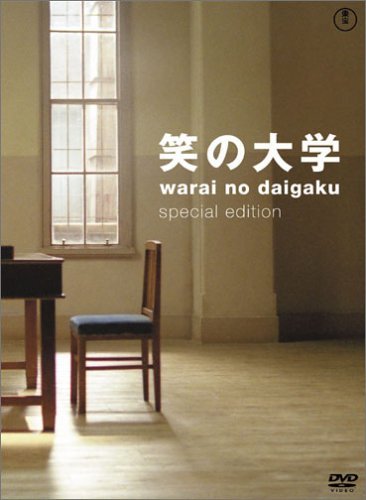昭和15年、戦争へと進む中、演劇や映画などの庶民の娯楽が規制されはじめていた頃のお話です。
台本には検閲があって、それにパスしなければ上演はできない。「笑い」は不謹慎で無意味であると排除するよう求める堅物の検閲官(役所広司)と、何としてでも上演に漕ぎ着けたい劇団「笑の大学」の脚本家(稲垣吾郎)が取調室で行うやりとり、交渉、駆け引きを軸に物語は進行します。軸に、どころじゃありませんね。ほとんどすべて、この取調室での二人の会話で成り立っています。
言葉のやりとりがこの映画のキモです。緊迫感があり、スピード感があり、徐々に表現される二人の心理がシーソーのように上下に動く躍動感ありで、正直なところ、まったく期待せずに観たのでこの完成度の高さには驚きました。
この映画で予想される二人の主人公の心的展開、それ自体は設定から誰もが想像できる範囲にあるわけですが、注目すべきはその展開に至る道筋を極めて慎重に描いているところです。安っぽいドラマに陥ることなく緩急を保ったままきっちりと誘導していくその脚本の技術力は驚くべきものです。
脚本の勝利であり、役所広司の演技力の勝利であり、稲垣吾郎の稚拙とも言える個性的な演技を効果的に引き出した演出の勝利ではないでしょうか。
この映画の話の中心が「演劇の脚本と検閲」という点も現代的です。ただの戦時中の昔話ではなくて、現代こそ問題にされるべき「言葉狩り」や「ファシズム的文化殺し」を戦時に置き換えているとも見えるわけです。そのテーマを小難しい芸術論や政治の話ではなく「笑い」に絞り込んでいる点が着眼点として見事だと思います。
映画・演劇をはじめ、文化、娯楽、芸術、芸能を愛する全ての人がこの映画を観て感情を揺さぶられることでしょう。
2007.01.23 hosoikobo