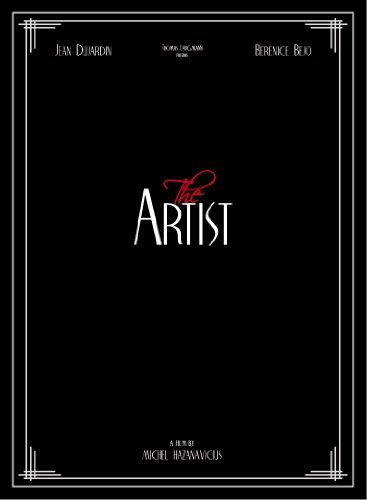私は年齢的にサイレント時代とかトーキーに移り変わっていく頃とかハリウッド黄金時代とか、そういうのは当然知りません。ただしそれらを体験してきた世代の影響を直接受けていますので、話に聞いたり名画座で観たり、テレビでやってたり、間接的には触れていなくもないかもしれません。20年代30年代という時代は別の意味での憧れの時代でもありまして、ハリウッドよりむしろパリとかですが、でもまあ時代の大きなうねりの中では似たようなものかもしれません。よくわかりません。その頃生きてないから。
サイレント映画の時代は知りませんが子供の頃は幻灯機というおもちゃみたいな映写機があって、もちろん声など出ないですからフィルムを送るカタカタという音を聞きながら漫画映画を楽しんだ記憶があります。何かのイベントで弁士つきのサイレント映画を観た記憶もかすかにあります。
時代を体験していなくてもサイレント映画や古いトーキーやハリウッドの華やかな映画文化の時代というものには懐かしさを感じます。これはきっとみんなそうじゃないでしょうか。そんなことないですか?きっと誰でもああいう雰囲気を懐かしいと思う心が植え付けられているように思いますがいかがでしょ。
そんな僕らのノスタルジーも直撃する「アーティスト」です。知らない過去を懐かしむという高度な精神活動を観る人全員に伝えるというとんでもない出来映えの映画です。
![アーティスト コレクターズ・エディション [Blu-ray]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51iJI%2B2vH-L._SX361_.jpg)
あまりにも高評価、あまりにもみんな絶賛、あまりにも大ヒット、そんなわけで今の今まで観ようと思わなかったのは、生意気にも「きっと観たら面白いだろうなあ。でもどのような面白さかはだいたい想像するとおりだろうなあ。だからまあ観なくてもいいか」なんて思っていて、ほんといつまで経っても学習しないあほたれです。何が「どんな面白さか観なくても想像できる」だ。なめとんのか。おれ。
で、観ました。もうね、たまんないです。

まだ負け惜しみを言いますが、観る前に考えていたとおりの、想像したとおりの面白さでした。でももちろんそれでいいのだ。ただし想像していた面白さの中で、想像を超えるほどの面白さでした。
まず最初なんと言っても映像の縦横比にあっと驚きました。あの比率で見せられたらたまりません。心理的にあのサイズは特別な映画に対する記憶に直結してますから、名作映画への期待やノスタルジーを縦横比だけで刺激してきます。あれ憎たらしい技ですね。
あと関心したのはノスタルジー系オーソドックスなシーンのカットの見事な尺です。どのシーンも昔なつかしのシーンやかつての名画からの引用で出来ていますが、もう少しやるとくどくなるぞという直前できっちり編集してます。この編集は抜群で、オーソドックスの美しいシーンをびしばし決めていく効果を上げています。いやほんとお見事。

でもこれをお見事と感じる人もいれば、すでにやり過ぎであると感じる人もいるようでして、オーソドックスを作った人たち、名画を名画たらしめた人たち、それらの支持者たちからすると、やっぱりちょっとやり過ぎのきらいはあるようです。つまりこの「アーティスト」という映画は、音楽でいえば名演奏を寄せ集めて作り上げたクラブ用のサンプリング音楽と同じようなものだからです。
サンプリングによって新しい価値を生み出すならともかく、過去の名演奏をそのままサンプリングして過去の名演奏のそっくりさんを作っただけなら、確かに価値ある創造とはあまりいえませんからね。
でもまあそこは評論家的な深い話もあってあれですので、この「アーティスト」という映画は新しい価値を生み出すタイプの映画ではありませんから私は気になりませんでした。むしろ昔風のそれ風のあれ風に仕上げることだけを目的化したような映画ですので、同じように古典の名作から引用したりして創造的ではない美に関与する私としましては職業的な意味でもこういうのを擁護したいところなのであります。
とはいえ、批判よりもやはり高評価が圧倒的。娯楽的に観た人は楽しむし批評家の支持も高い、アカデミー賞も多部門受賞、カンヌでも上映されました。そういえばアメリカの映画職人のための内輪の賞であるアカデミー賞で外国映画が作品賞を受賞するのは史上初とのことですね。
ストーリーはオーソドックスでキュート。犬も大活躍。カンヌでパルムドッグ賞もとりました。
筋の流れと面白さは何から何まで狙い通りです。でもぐっときます。
その中で現代的というか特徴的だと思ったのは、ひたすら少女小説のような女優の性格や筋の流れです。何がどう少女小説なのかはくどくど書きませんけど、これおもくそ少女小説ですよね。ピュアで可愛くて一途な女優の姿が胸を打ちます。
アートは逃げ口上か
映画「アーティスト」の中で大きな問題を提起している部分があります。サイレントからトーキーへの流れの中で、古いシステムにこだわる主人公が自分のその方向性を「アート」だと認識しているという部分です。トーキーなんてのは大衆に媚びただけの単なる流行で、映画としてアートではないというわけですね。
そう言いながら主人公が作るサイレント映画が果たしてアートなのかどうなのかは疑わしい限りです。
サイレントからトーキー、モノクロからカラー、そして最新の事象であるフィルムからデジタル。技術による変遷の中で従来の技法にこだわる人は必ず「アート」と口にします。
「サイレントこそ映画でありアートだ。声が出るなど、そんなのは色物にすぎない」
「モノクロ映像こそ映画でありアートである。色がついているなど下品きわまりない」
「フィルムで撮ってこそ映画でありアートである。デジタル臭いビデオ画質の安っぽさなどとんでもない」
この問題は映画とアートに限らず、音楽、文学、あらゆる文化・芸術の中で議論されてきたことのように思います。
ある意味、売れない芸術家、あるいは最新技術についていけない人々の負け犬の遠吠えであり逃げ口上です。そして別のある意味では正しいことでもあります。
この件に関して書いていくと止め処がなくなりますので、逃げ口上であるけれど正しいことであると書くに留めておきます。
※ このページの画像は Amazon アーティスト・コレクターズ・エディションDVDの紹介ページのものです